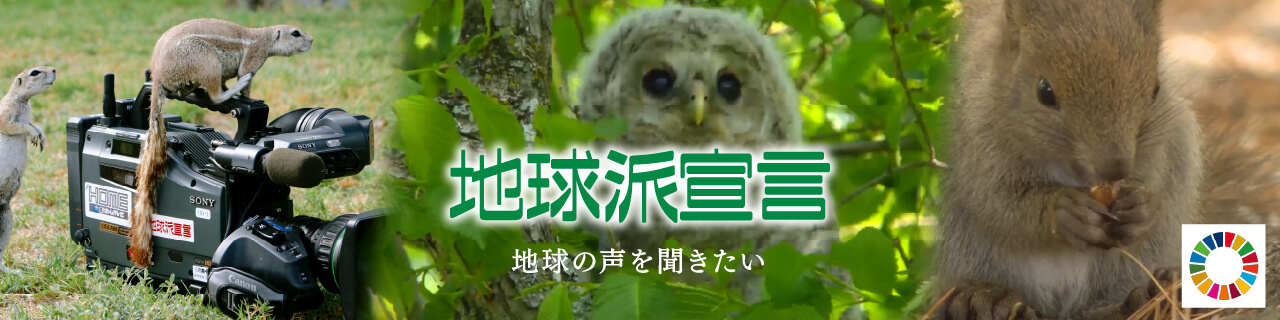世界中を取材した自然を紹介し、環境に関心を。
アオウミガメ/小笠原
春になると、大きなアオウミガメたちが本州の方から交尾・産卵のために小笠原諸島へやってきます。ここは日本最大のアオウミガメの繁殖地です。その昔は今よりもたくさんのウミガメがいましたが、戦前の乱獲により激減してしまいました。現在は規則の制定や保全活動がぬを結び、小笠原に繁殖に来るウミガメの数は増加傾向にあります。
スイレン/呉市
呉市・野呂山にある氷池。標高839mの山頂にあり麓より5度も気温が異なるといわれます。明け方から夕方にかけて花が開くスイレンは8月中旬ころまで楽しめます。花は未(ひつじ)の刻、(午後2時ごろ)に咲かすとされ、名前の由来となりました。ただ、実際はお昼前後から開き始め、夕方以降にしぼんでしまいます。
サクラ/三原市・佐木島
三原市の離島、佐木島の塔の峰に植えられた「千本桜」が満開を迎えました。市を代表する名所の1つで対岸からも確認できるほどです。島の人たちが1991年から荒れたミカン畑を手入れし、約1300本を植樹しました。
メジロ/広島市南区
全長11.5cm。日本では全国の平地から山地の林にすんでいます。目のまわりの白いフチドリ、スズメよりやや小さく、頭から背中は黄緑色で喉は黄色く、腹は白っぽいのが特徴。留鳥として一年中見られます。小さな昆虫やクモ類を主食とするが、ツバキやウメ、サクラなどの花蜜をよく吸い、受粉を助けます。
キリン/ナミビア
「静かなる絶滅」に向かっていると言われているキリンが、新たな調査によると、個体数を増やしつつあるといわれています。これまでアフリカ全体で生息数が8万~9万頭に達するキリンは絶滅の恐れが低いとみられていました。そんな中、遺伝子でグループ分けすると明確に4種に分かれ、最も少ないものは5千頭を切っているといわれます。
センダン/三次市
センダンの花は、淡紫色の小さな花で、バニラやチョコレートのような甘い香りがします。若葉の先に円錐形の花序を出し、5枚の花弁からなる花を多数咲かせます。花期は5~6月です。古くは「アフチ(オウチ)」と呼ばれ万葉集や枕草子などの古典文学にも登場する植物です。
リュウキンカ/北広島町
立金花(リュウキンカ)とは、その名のとおり茎が立ち上がって黄金色の花を付けることに由来します。
春先、湿地などでよく見かける多年草で、北海道や東北地方など寒い地域に分布している。湿地の好きなミズバショウと一緒に咲いていることも多く、黄金色の美しい花の姿は春を感じさせてくれます。花には花弁がなく、花弁状のガク片が普通5枚ある。
カンムリカイツブリ/三次市
全長56㎝。首が長く、水面に軽く浮いている水鳥です。頭上に黒色の冠羽があります。脚は体の後方に付いていて、脚だけで潜水ができます。飛行時は脚が短い尾をこえて後方へ伸びているのが見えます。日本では冬鳥として渡来していますが、およそ50年前に本州北部で繁殖が知られるようになりました。