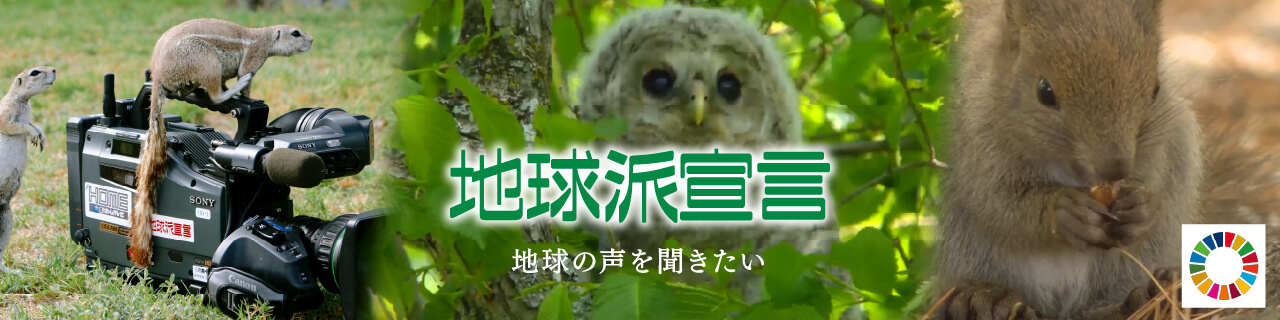2024年度放送分
バイカモ/庄原市
バイカモはキンポウゲ科の淡水植物で梅の花に似た、白い小さい花を5月中旬~9月下旬まで咲かせ、7月下旬~8月下旬にかけて見頃を迎えます。梅花藻と呼ばれ、水温14℃前後の清流にしか育たず、全国でも生育場所が限られています。
ブッポウソウ/三次市
毎年、5月のゴールデンウィークになると、〝ゲゲゲー〟という鳴き声とともに色鮮やかな青い羽根のブッポウソウが私たちの町に子育てにやってきます。水田や川があり、近くに親鳥が見張りをできる小高い山や木があるような開けた場所で、山の中ではなく、人里を好みます。
キジバトよりやや小さく、体は光沢がある青緑色で、飛ぶと大きな白斑が目立ちます。鎌倉時代からコノハズクの鳴き声に誤認され、仏法僧と呼ばれたとか。近年、営巣木の伐採や昆虫の減少などで激減し、電柱に巣箱をかける保護活動が始まりました。
羽衣の滝/北海道
羽衣の滝は、大雪山国立公園内の天人峡にあり、忠別川支流のアイシポップ沢と双見沢からの流れが7段に屈折しながら落下し、滝の途中で2つの沢が合流しています。高さ270メートルの絶壁を7段に屈折しながら落下しており、落差は北海道一を誇っています。「日本の滝百選」にも選ばれています。
リトルファイルフィッシュ/フィリピン
生き物は様々な方法で獲物をとったり、身を守ったりしています。フィリピンの海の中…ソフトコーラルの合間に隠れている魚、リトルファイルフィッシュ。体をサンゴの仲間などに似せ、敵から身を守ります。
エドヒガン/庄原市
庄原市東城町にある飯山。その北東の山麓にエドヒガンが生育しています。東城三本桜の1つで、胸高幹囲4.5mを超え、広島県内では3番目に大きいとされています。広島県内では,自生は少ないが,植栽されて育ったものが各地にあり,特に県東部にいくつかの大木が見られます。県の天然記念物にも指定されています。
アカアシドゥクラングール/ベトナム
アカアシドゥクラングールはベトナムなどの熱帯雨林に生息しています。樹上に暮らし、木の葉や果物が主食です。足が赤茶、顔が白など体の部位で毛色が異なり、その体の色の多さ、美しさから「世界で一番美しいサル」とも言われています。熱帯雨林およびモンスーン林に10頭程の群れで生活しています。ベトナム戦争の時に、米軍によって散布された枯葉剤によって生息地の大半を失って数が激減したと言われており、生存が極めて危険な状態にあります。
キョウシギ/福山市
福山市松永湾で撮影されたキョウシギ。全長約22cmでシギの中では短い足をしています。たくさんいるシギの仲間の中でも、夏羽のときは白・黒・栗色のまだら模様が、京の女が着る衣裳のような派手な色彩をしているところから「京女(キョウジョ)」シギになったといいます。一般的な旅鳥で春と秋に日本を通過していきますが、春に多く通っていきます。冬羽は、他のシギのようにずっと地味になります。上にややそりかえったくちばしで海草や小石を掘りかえし、中からとび出す虫などを食べています。
ガガブタ/三次市
ガガブタは池などの浅いところに群生する常葉性の多年草です。 葉の表面は濃緑で光沢ある辺縁から葉の中心に向かって蝶形の褐色斑があるのが特徴的。
花期は7~10月初めまで葉柄基部に白色の束状花序が生じています。
国内では生育場所であるため池や湖沼の水質汚濁や改修工事、埋め立てなどによって減少しつつあり、環境省レッドリスト2018では「準絶滅危惧」とされています。
サンカヨウ/庄原市
サンカヨウは山地の湿原に生える多年草で、小さな白い花を咲かせます。別名は「スケルトンフラワー」。「山荷葉」という和名は、「山に生えハスの葉に似ている」ことが由来です。茎に直径2cmほどの白い6弁花を数個咲かせ、雨に濡れると透明に。開花すると、わずか1週間ほどで散ってしまうため、花が咲いているところを見るのは、かなり難しいとされています。
スナガニ/広島市
スナガニは砂浜の波打ち際付近に巣穴を作って生息する、甲らの幅(甲幅)が3㎝ほどのカニです。両眼が大きくて警戒心が非常に強く、人の気配を感じると、砂地に掘った巣穴に素早く逃げ込みます。巣穴の開口部の直径は1~3㎝ほどで、その周辺にはたくさんの砂団子が見られます。夜行性のカニなので、昼間は巣穴に入っていることが多く、おもに夜間に活発に活動します。6月から9月がおもな活動時期で、冬期は砂の中で越冬します。6月から9月がおもな活動時期で、冬期は砂の中で冬眠します。以前は多くの砂浜海岸で数多くのスナガニを観察することができましたが、現在は各地で個体数が減少しています。
ギンポハゼ/沖縄県・西表島
ギンポハゼの求愛行動は非常にユニーク。繁殖期になるとオスは求愛時に体色が変化することがあります。鮮やかな色彩を見せてメスにアピール。自分の大きさや健康状態をアピールします。特に背鰭を大きく広げる動作が目立ちます。メスはそれを見て最も魅力的なオスを選ぶのです。
三瓶山/島根県
島根県にある三瓶山は中国地方にある活火山の1つで、最後に噴火したのは、約4千年前です。秋になると、紅葉が山全体を彩り、絶景を楽しむことができます。紅葉は、10月下旬から11月上旬にかけて見頃を迎えます。
シラネセンキュウ/島根県益田市
林の中や川の近くなど湿った日陰に生える多年草で、本州から九州にかけて見られます。花期は9~11月で、小さくかわいらしい花でたくさん集まって咲くため存在感があります。別名をスズカゼリともいいます。
ベニマンサク/廿日市市
「幸福の再来」などの花言葉を持つ、ベニマンサク(紅満作)の木。ハート型の葉っぱがかわいらしく、とりわけ秋には美しくまたかわいらしい紅葉を見せてくれます。「おおの自然観察の森」では県の天然記念物に指定されているベニマンサク群落が多くみられます。
ミーアキャット/ナミビア
地下トンネルを掘って10~30頭の群れで暮らしているミーアキャット。群れの中では見張り役やベビーシッターなど役割が分担され助け合って生活している。ミーアキャットは直立して太陽の光を浴びて日光浴することにより、身体を温めています。アフリカの砂漠地帯は夜間、大変冷え込むため太陽が登ると日光浴をして体を温めて活動します。
ハッチョウトンボ/世羅町
世界最小級のトンボのハッチョウトンボ。世羅にある自然観察園にある300平方メートル余りの湿地に生息しています。体長は2センチほどで背が赤いのがオス、黄色と黒の横縞があるのがメスです。県のレッドデータブックに登録され絶滅が心配されています。
クマタカ/北広島町
日本から中国南部、ヒマラヤなどに分布していて、日本ではほぼ全国で繁殖しています。日本の森に生息する大型猛禽「クマタカ」は独自進化を遂げた固有亜種として知られ、環境省レッドリストで絶滅危惧種に指定される。
ハナゴイ/沖縄・石垣島
ハナゴイは全長約12cmで、潮通しのよいサンゴ礁の外縁部に群れで生息しています。体はやや細長く鮮やかな赤紫色で水槽ではとても目立つ存在です。雄は成長すると鼻先が尖り、背は伸張し、背のビレ後ろは濃い赤色を呈します。また、尾ビレが黄色くなることもあるため、成魚になれば雌雄の区別は容易にできます。
サギソウ/三次市
サギソウは日当たりの良い湿地に自生する野生のランの一種です。白鷺が羽を広げたような形の白い花を咲かせます。園芸用として人気が高まったことによる乱獲や環境の変化によって、国内各地で自生地は減っています。
ゴギ/島根県浜田市
ゴギは、中国地方の清流にひっそりと暮らす「幻の魚」として知られています。紅葉が色づく美しい季節、礫底を産卵床として選び、子孫を残します。急流を好み、大きな岩の陰に身を潜める姿は、まさに自然との共存を象徴しているかのようです。しかし、河川改修などによる環境の変化に非常に弱く、その生息数は年々減少しています。
オオハクチョウ/北海道
毎年、本格的な冬を前に、繁殖地のロシア北東部から日本へと渡ってくるハクチョウ。北海道に飛来するその姿は、美しい白羽と優雅な動きで多くの人々を魅了します。この地は、本州へ向かうオオハクチョウたちが羽を休める中継地となっています。親子連れが水辺で餌をついばんだり、羽を繕ったりする姿は、冬の北海道の風物詩です。しかし、近年は地球温暖化の影響で、渡りのパターンや越冬地に変化が生じている可能性も指摘されています。
ハイラックス/ナミビア
ハイラックスは、一見ネズミのような可愛らしい外見をしていますが、実はゾウやジュゴンと同じ祖先を持つ、意外な動物です。乾燥したアフリカの岩場や草原に生息し、30頭から80頭程度の群れを作って生活しています。肉球が吸盤のように機能するため、垂直な岩壁も難なく登ることができます。
河津桜/三次市
静岡県の河津町で偶然発見された河津桜は、毎年2月上旬頃から咲き始め、早咲きの桜として知られています。昭和30年ごろ、河津川沿いで見つけられた一株が、その美しい花を咲かせる様子から大切に育てられ、品種として定着しました。一般的な桜が短い期間に一斉に花開くのに対し、河津桜はゆっくりと花を咲かせ、長い期間私たちを楽しませてくれます。
常清滝/三次市作木町
常清滝は、広島県北部・三次市作木町に位置する、高さ126メートルの雄大な滝です。日本の滝百選にも選ばれ、日光の華厳滝や熊野の那智滝と肩を並べるほどの壮観な姿を見せてくれます。1960年には広島県の名勝に指定され、その美しさは多くの人々を魅了し続けています。
ビワの花/東広島市
ビワは、6月に黄色く熟した果実を私たちに届けてくれる一方で、11月中旬から2月上旬という寒い時期に花を咲かせる、不思議な植物です。枝いっぱいに小さな白い花を咲かせ、その数は日に日に増え、花の色は白から黄色へと変化していきます。同時に、甘く芳醇な香りが辺りに漂い始め、メジロやヒヨドリなどの小鳥たちを誘います。
アオバト/三次市
全体が緑色をした羽が特徴のアオバト。オスは肩の部分がブドウ色と、メスとは異なる美しい色彩を見せてくれます。山地から平地まで、様々な環境に生息するアオバトですが、特に果実が豊富な広葉樹林を好み、そこで群れを作って生活しています。一部の個体は冬になると暖かい地方へ移動しますが、多くは日本に留まって越冬します。興味深いことに、東北地方ではその特徴的な鳴き声から「魔王鳩」という呼び名で親しまれてきたようです。
オキナグサ/三次市
オキナグサは、本州、四国、九州の日当たりの良い草原や林縁に生える、優しい雰囲気の多年草です。茎や葉全体を覆う白い毛は、その印象をさらに深め、まるで冬枯れの草原に舞い降りた雪のようにも見えます。近年は開発や乱獲などにより自生地が減少し、その姿を見る機会が少なくなっています。日本の原風景を彩る貴重な植物として、オキナグサの保護が求められています。
ヤブツバキ/山口県長門市
北長門海岸国定公園では、冬から春にかけて鮮やかに咲き誇るヤブツバキが自生しています。日本を代表する花木の一つであるヤブツバキは、特に温暖な北長門海岸のような地域では、海風に揺られながら力強く花を咲かせ、冬の寒さを彩ります。厚く重なり合った花弁と、中心に集まる黄金色の雄しべのコントラストが美しく、豪華な印象を与えます。